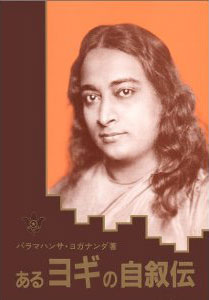午前は、聖女ベルナデッタの生家、聖女の遺品、受洗の教会などを巡礼。最後に向ったホスピスは、聖女が聖母を見てからヌヴェールの修道院に発つまでの間に暮らした場所だ。
われわれが入っていくと、たまたま一人のシスターが聖堂での祈りを終えて出てこられた。ベルナデッタが入ったヌヴェール愛徳修道会のシスターである。
まず聖堂を見せていただくと、シスターは何やらフランス語でまくしたてる。そうして示されたのは、聖女の使っていた頭巾だった。頭巾には少量の髪の毛が添えられていたが、それが、まさに聖女の遺髪であった。
次いでシスターが取り出されたのは、一つの顕示台。ガラスの中にあるのは、聖女が葬られて30年後、遺体が発掘されたときに採取されたという胸の骨だった。そのようなものを拝見できるとは思ってもいなかったが、それにしても……と思う。腐敗を免 れた聖女の遺体に、彼らはメスを入れたらしい。文化の違いか。
(クリックで画像拡大)

聖遺骨