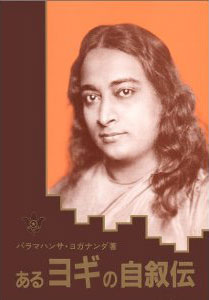(久々のアジアの旅となった第11回『大いなる生命と心のたび』は、先般、全員が元気にお帰りになり、また、私も遅れて帰国した。恒例の旅日記を、少々遅れて掲載したい。)
いつも通り、睡眠2時間で空港へ向かう。そしていつも通り、久しぶりにお会いする皆さん、初めてお目にかかる皆さんを目の前にしてすっかり疲れを忘れる。
世界一のサービスと定評があるシンガポール航空で、まずはシンガポールへ。着後、入国手続きを済ませ、バスに乗り込む。すべてが清潔で、スピーディーな国だ。
バスの前で待っていたのは、顔も体型も、大相撲の小錦を一回り小さくしたような男だった。ところがこの人、日本語が上手い。団地やマンション、戸建て、車の値段を引き合いに出しながら、巧みにシンガポール人の暮らしぶりを説明してくれる。
ついにオーチャードロードに入るや、思わず歓声。クリスマスのイルミネーションで、街全体が輝いている。今まで何度もシンガポールに来たが、この季節は初めてで、華やかさに驚いてしまう。
続いて、クルージングへ。だが……やって来た船を見て一同ふたたび驚く。ついさっきまでの都会の華やぎから一転して、来たのは古きよき時代の木造船。いやいや、難民船だという声も。
船の中ではシンガポールの歴史を日本語で聞き、美しい夜景を見ながら、マーライオンの港に着く。機内では、食後のデザートに大きなアイスクリームが配られたが、女の子たちはここでふたたびアイスクリームへ。
空港への帰路、小型小錦にいろいろな質問をして盛り上がる。しかしそれにしても、どうしてそんなに日本語がうまいのか。そう聞くと、彼は笑って言った。
「私、実は小錦の弟なんです」
(クリックで画像拡大)

アイスクリームの少女たち