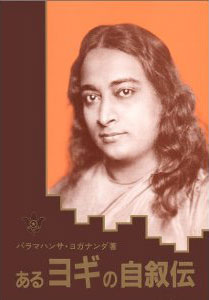常々、タバコの煙にいい思いをしていない。
臭い、というレベルの話ではない。敏感な人は、副流煙によりアレルギー性鼻炎を誘発する。頭痛がする。気持ちが悪くなる。風邪をひきやすくなる。愛煙家は、自分が食事を終えると美味そうにタバコを吸うが、周りはせっかくの食事がまずくなる。味覚は、常に嗅覚と共同で働いているからだ。風邪で鼻がつまると食べ物の味がしなくなるのは、その理由による。
そんなの、ちっとも気にならない、という人もいる。が、そういうタフな人でも、実は副流煙によって刻々と健康は損なわれている。副流煙が、主流煙に比べて数倍から数十倍、ものによっては百数十倍の発ガン物質を含むことは、単純な測定で得られる事実である。
愛煙家の多くは、タバコが自分の健康だけではなく、他人の健康をも損ない、不快感を与えているという事実を、実は知っている。が、それを認めたくはない。自分が長年にわたって他人に迷惑をかけているという事実を、誰がすすんで認めたいだろう。
それでも、ぼくは知っている。多くのタバコ吸いが、他人の前では平気でタバコを吸うのに、自分の子供の前では注意深く喫煙を避けるのを。
青山圭秀
おすすめDVD
推薦書籍
-
最近の投稿
最近のコメント
- 『五輪 9』―4連覇― に SHO より
- ダルマ(番外編) に ハルク より
- ダルマ8 に SHO より
- ダルマ(番外編) に SHO より
- ダルマ8 に SHO より
コメント投稿につきまして
<プレマ倶楽部>会員の方のみ投稿が可能です。お知らせしております会員用ID(ユーザー名)とパスワードでログインしてください。IDをお忘れになった場合は、<プレマ倶楽部>事務局までお問い合わせください。
詳しいコメントの投稿方法につきましては、こちらの<プレマ倶楽部>会員様専用ページをご覧ください。アーカイブ
- 2016年8月 (9)
- 2015年12月 (1)
- 2015年9月 (6)
- 2015年8月 (5)
- 2014年9月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (10)
- 2013年7月 (4)
- 2013年6月 (13)
- 2013年5月 (2)
- 2013年3月 (4)
- 2013年1月 (6)
- 2012年12月 (10)
- 2012年11月 (5)
- 2012年10月 (2)
- 2012年9月 (1)
- 2012年8月 (6)
- 2012年7月 (11)
- 2012年6月 (21)
- 2012年5月 (7)
- 2012年4月 (1)
- 2012年3月 (13)
- 2012年2月 (8)
- 2012年1月 (16)
- 2011年12月 (9)
- 2011年11月 (3)
- 2011年10月 (2)
- 2011年9月 (3)
- 2011年8月 (4)
- 2011年7月 (3)
- 2011年6月 (1)
- 2011年5月 (1)
- 2011年4月 (5)
- 2011年3月 (5)
- 2011年2月 (8)
- 2011年1月 (3)
- 2010年12月 (9)
- 2010年11月 (3)
- 2010年10月 (9)
- 2010年9月 (2)
- 2010年8月 (3)
- 2010年7月 (3)
- 2010年6月 (1)
- 2010年5月 (6)
- 2010年4月 (3)
- 2010年3月 (13)
- 2010年2月 (6)
- 2010年1月 (5)
- 2009年12月 (1)
- 2009年11月 (9)
- 2009年10月 (16)
- 2009年9月 (3)
- 2009年8月 (8)
- 2009年7月 (2)
- 2009年6月 (14)
- 2009年5月 (10)
- 2009年4月 (2)
- 2009年3月 (4)
- 2009年2月 (5)
- 2009年1月 (2)
- 2008年12月 (5)
- 2008年11月 (7)
- 2008年10月 (25)
- 2008年9月 (30)
- 2008年8月 (7)
- 2008年7月 (3)
- 2008年6月 (10)
- 2008年5月 (1)
- 2008年4月 (9)
- 2008年3月 (10)
- 2008年2月 (4)
- 2008年1月 (13)
- 2007年12月 (1)
- 2007年11月 (29)
- 2007年10月 (29)
- 2007年9月 (30)
- 2007年8月 (32)
- 2007年7月 (23)
- 2007年6月 (7)
- 2007年5月 (3)
- 2007年4月 (4)
- 2007年3月 (8)
- 2007年2月 (1)
- 2007年1月 (6)
- 2006年12月 (6)
- 2006年11月 (24)
- 2006年10月 (4)
- 2006年9月 (10)
- 2006年8月 (23)
- 2006年7月 (5)
- 2006年6月 (3)
- 2006年5月 (4)
- 2006年4月 (3)
- 2006年3月 (9)
- 2006年2月 (19)
- 2006年1月 (8)
- 2005年12月 (6)
- 2005年11月 (15)
- 2005年10月 (4)
- 2005年9月 (13)
- 2005年8月 (13)
- 2005年7月 (11)
- 2005年6月 (16)
- 2005年5月 (31)
- 2005年4月 (35)
- 2005年3月 (7)
- 2005年2月 (8)
- 2005年1月 (4)
- 2004年12月 (15)
- 2004年10月 (4)
- 2004年9月 (4)
- 2004年8月 (14)
- 2004年7月 (5)
- 2004年6月 (10)
- 2004年5月 (2)
- 2004年4月 (11)
- 2004年3月 (16)
- 2004年2月 (15)
- 2004年1月 (1)
- 2003年12月 (6)
- 2003年7月 (14)
- 2003年3月 (4)
- 2003年2月 (2)
- 2003年1月 (7)
- 2002年12月 (5)
- 2002年11月 (12)
- 2002年10月 (4)
- 2002年8月 (8)
- 2002年7月 (9)
- 2002年6月 (8)
- 2002年5月 (1)
- 2002年4月 (6)
- 2002年3月 (7)
- 2002年2月 (4)
- 2002年1月 (3)
- 2001年12月 (11)
- 2001年11月 (1)
- 2001年7月 (8)
- 2001年6月 (4)
- 2001年5月 (8)
- 2001年4月 (7)
- 2001年3月 (6)
- 2001年2月 (2)
- 2001年1月 (4)
- 2000年12月 (3)
- 2000年7月 (7)
青山圭秀の『瞑想録』旧サイト
カテゴリー
メタ情報